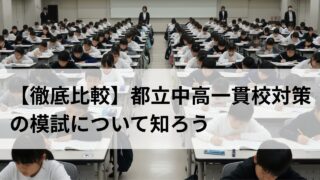- 通信教育を検討しているが、どれが良いか迷っている
- Z会小学生コースの内容や費用など基本情報が知りたい
- Z会会員の方のリアルな声が知りたい
- 紙教材かタブレット教材はどっちが良いのか分からない
子どもに学力をつけさせたいけど、習い事も続けさせたいので塾は難しい。。。
そんなご家庭の場合、通信教育というのは選択肢になるでしょう。ただ、一言で通信教育と言っても、たくさんあって正直どれが良いか分からないという声も多いかと思います。

私の娘は小学生1年生~4年生の途中までスマイルゼミで学習していましたが、小学5年生からZ会小学生コース(紙教材)と適性検査講座を受講しています。
Z会の特徴を挙げると
- 通信教育の顧客満足度最優秀賞を何度も受賞
- 良問ぞろいで教科書+αの学びが得られる質の高い学習内容
- 担任指導者制で丁寧な添削指導
- 学習カレンダーで自発的な学習習慣が身につく
- 付録やゲームが無いので、学習により集中できる
スマイルゼミとZ会を経験した娘の学習状況を見ていると、娘にとってはZ会小学生コースの方が合っている様に感じます。
お子さんの学力や性格、そして学校以外の学習を行う目的などによって、どの通信教育が合っているかは変わってくるでしょう。学校の学習をより理解するためなのか、それとも中学受験を目指すためのかなど、通信教育を行う動機は様々だと思います。
今回はZ会小学生コースおよび小学生タブレットコースを中心に、学習内容や特徴、費用、口コミなどについてまとめてみました。また、紙教材かタブレット教材のどちらを選ぶべきかについても、私見を交えながら述べています。
数ある通信教育教材で迷っている方にとって、Z会の良さを知ってもらえるような記事となれば幸いです。
それでは興味のある方はぜひ続きもご覧ください。
期間限定で特典プレゼント
2026年2月27(金)〆切
小学生向けコースの種類
Z会の小学生向けのコースを細かく分類すると以下の通りです。
- 小学生コース(1・2年生)
- 小学生タブレットコース(1・2年生)
- 小学生コース(3~6年生)
- 小学生タブレットコース(3~6年生)
- 中学受験コース(3~6年生)
小学生コースは紙を使った教材、小学生タブレットコースは配信されるデジタル教材を使用します。
中学受験コースは難関国私立中学を受験するご家庭に向けたコースとなっています。今回の記事では、小学生コースおよび小学生タブレットコースの内容を中心にまとめています。
受講できる科目
受講できる科目は各コースごとに異なります。
小学生コース(1・2年生)と小学生タブレットコース(1・2年生、3~6年生)は全科目のセット受講のみとなりますが、小学生コース(3~6年生)は1教科からの受講も可能です。
上記のコースに加え、小学生コース(1・2年生)にはオプション講座を、小学生コース(3~6年生)、小学生コースタブレットコース(3~6年生)を目的別講座を受講することができます。
各コースで受講できる教科をまとめてみます。
小学生コース(1・2年生)
- 国語
- 算数
- 経験学習
- 英語
- プログラミング
「経験学習」は、社会や理科につながる工作、実験、社会体験を通じて学習するZ会オリジナル教材です。国語、算数、経験学習は紙の教材を使用しますが、英語とプログラミングに関してはデジタル教材となります。
また、オプション講座の「みらい思考力ワーク」という講座を加えることができます。これは様々な問題に取り組む中で知識の活用方法を身につけ、将来につながる思考力の土台を築くための講座となっています。
小学生タブレットコース(1・2年生)
- 国語
- 算数
- みらいたんけん学習
- 英語
- プログラミング
このコースはすべてタブレットによるデジタル教材です。
「みらいたんけん学習」とは、社会と理科につながる知識と、教材にとらわれない思考力を身につけるオリジナル教材です。
小学生コース(3~6年生)
- 国語
- 算数
- 理科
- 社会
- 英語
- プログラミング学習
英語は5・6年生になると月1回のオンラインスピーキングレッスンも受講できます。このレッスンとプログラミング学習以外は紙の教材を使用します。
小学生コースは1教科からの受講も可能で、苦手科目だけ学習できるのは良い点と言えるでしょう。
また、上記の講座以外に目的別講座を追加で受講することもできます。
- 思考・表現力(3・4年生)
- 作文(5・6年生)
- 公立中高一貫校適性検査(5・6年生)
- 公立中高一貫校作文(6年生)
小学生タブレットコース(3~6年生)
- 国語
- 算数
- 理科
- 社会
- 英語
- 未来探求学習
- プログラミング学習
小学生タブレットコースは全てがタブレットを使用したデジタル教材となります。英語は小学生コースと同様にオンラインスピーキングレッスンが月1回受講できます。
「未来探求学習」は、教科の超えた幅広い知識を組み合わせ、自分で考える力を身につけるオリジナル教材となっています。
また、上述した小学生コースと同じく、目的別講座を加えることも可能です。
Z会小学生コースの特徴
Z会の通信教育における特徴は以下のようなものがあります。
- 顧客満足度調査の通信教育部門でNO.1の評価
- 教科書+αの学びでハイレベルな学力が身につく
- 担任指導者制により、一人一人に合わせた丁寧な添削指導
- 自発的に学びの習慣がつきやすい学習カリキュラム
- 付録やゲームは無いので、より勉強に集中できる
Z会はイード・アワード顧客満足度調査で、何度も通信教育部門で最優秀賞を受賞してます(イード・アワード2025年度はこちら)。

通信教育には様々なものがありますが、多くの方に支持されていることが分かりますね!
また、Z会は教科書よりも少し高いレベルの問題が出題されます。応用、発展問題の割合が多いので、高いレベルの学力を身につけることが期待できます。
添削問題については、担任指導者制となっていることで、丁寧な添削指導が行われています。学習カレンダーで日々の学習が見える化されている点や、適切な難易度かつ適度な学習量によって、学習習慣がつけやすい構成となっているのも大きなポイントです。
通信教育によっては、付録やゲームがついている教材もありますが、Z会にはその様なご褒美的なものはありません。一方で少し難しいくらいのレベルが出題されるので、純粋に学習への楽しみ、分かった時の喜びなどが感じられるのではないかと個人的には感じています。
小学生コース学習の流れ
学年そして紙またはタブレットコースによって、若干の流れは異なりますが、基本的には以下の流れで学習を進めます。
- 学習計画を立てる
- 教材で学習する
- まとめテスト・提出課題で習熟度チェック
- 翌月の計画を立てる
- 提出課題の復習(返却後)
まずは計画を立てることから始まります。紙教材であれば学習カレンダーにシールや書き込みを行い、自分でスケジュールを調整します。タブレットコースは自動でスケジュールが配信されますが、予定に合わせて自分で調整することも可能です。
次にスケジュールに沿って学習を進めます。全て終わるとタブレットコース1,2年生であれば「まとめテスト」、その他のコースでは「提出課題」に取り組みます。
また月末には翌月の教材が届きますので、改めて学習計画を立てます。
添削問題については返却後に復習を行います。提出のタイミングにもよりますが、翌月にまたぐこともあります。

基本的には学習計画⇒学習⇒添削問題⇒学習計画の流れですね!
受講費用(コースおよび学年別)
次に受講費用について見ていきましょう。
まず料金の幅は以下の通りです。
- 小学生コース 5,320円~11,460円
- 小学生タブレットコース 4,465円~10,925円
上の金額は、目的別講座を除き各コースの全科目受講した場合の金額です。1年生から6年生にかけて金額が上がります。
- 2,280円~3,800円
目的別講座は3年生以上で追加で受講できる科目です。
以下に詳細な月額費用を以下の表まとめました。1教科のみの受講料と5科目セット(プログラミングも含む)の受講料を載せております。4教科から2教科の料金については、Z会のHPをご確認ください。
本来、支払いは方法は12か月一括払い、6ヶ月一括払い、1か月払いがあり、本来は12か月払いが最も安くなります。しかし、記事執筆時点(2025年9月)で申込む場合は10月号が開始月となり、各講座の年度終了月までが6ヶ月以下になります。この場合12か月一括払いを選択することができません。そのため以下の表では、1か月払いまたは6ヶ月払いのみを掲載しております。新年度には12か月一括払いを選択することができます。
小学生コースの月会費
| コース名 | 1カ月払い (月額) | 6カ月一括払い (月額) |
|---|---|---|
| 1年生(みらい思考力ワークなし) | 5,600円 | 5,320円 |
| 1年生(みらい思考力ワークあり) | 6,600円 | 6,270円 |
| 2年生(みらい思考力ワークなし) | 5,880円 | 5,586円 |
| 2年生(みらい思考力ワークあり) | 6,880円 | 6,536円 |
| 3年生(5教科セット) | 9,700円 | 9,105円 |
| 3年生(1教科のみ) | 2,380円 | 2,261円 |
| 4年生(5教科セット) | 10,600円 | 9,960円 |
| 4年生(1教科のみ) | 2,560円 | 2,432円 |
| 5年生(5教科セット) | 12,200円 | 11,460円 |
| 5年生(1教科のみ) | 2,960円 | 2,812円 |
| 6年生(5教科セット) | 12,200円 | 11,460円 |
| 6年生(1教科のみ) | 2,960円 | 2,812円 |
小学生タブレットコースの月会費
| コース名 | 1カ月払い (月額) | 6カ月一括払い (月額) |
|---|---|---|
| 1年生(セット料金) | 4,700円 | 4,465円 |
| 2年生(セット料金) | 5,100円 | 4,845円 |
| 3年生(セット料金) | 8,800円 | 8,360円 |
| 4年生(セット料金) | 9,400円 | 8,930円 |
| 5年生(セット料金) | 10,500円 | 9,975円 |
| 6年生(セット料金) | 11,500円 | 10,925円 |
目的別講座の月会費
| コース名 | 1カ月払い (月額) | 6カ月一括払い (月額) |
|---|---|---|
| 思考・表現力(3・4年生向け) | 2,400円 | 2,280円 |
| 作文(5・6年生向け) | 4,000円 | 3,800円 |
| 公立中高一貫校適性検査(5年生向け) | 3,700円 | 3,515円 |
| 公立中高一貫校適性検査(6年生向け) | 4,000円 | 3,800円 |
| 公立中高一貫校作文(5・6年生向け) | 4,000円 | 3,800円 |
※記載の料金はすべて税込みです。
※上記の料金は2025年9月時点のものです。料金は変動することがありますので、最新の情報は必ず公式サイトでご確認ください。

受講料金を比較すると、タブレットの方が紙の教材よりも安いことが分かりますね。
毎月の学習量は?
学習量や学習時間は学年、コースにより少し異なります。小学1年生から6年生にかけて徐々に増えていきます。
- 1年生が約15分/日、6年生でも約30~40分/日で1か月の学習量が終わるカリキュラム
- 紙とタブレットでは、タブレットの方が学習時間が短い傾向
標準の科目を受講した場合の目安時間は上記の通りです。タブレットですと自動解答だけに、時間が短縮されている部分もあるでしょう。
公式サイトには、各コースで学年ごとの学習量が記載されていますが、以下に各学年ごとで2つのコースで学習量がどう違うかを比較してみました。
1年生の学習量
小学生コース
【1日の学習時間目安】 約15分
| 教材 | 1回学習量(目安時間) | 回数 |
| メインテキスト(国、算) | 10分 | 各10回/月 |
| ドリル(国、算) | 5分 | 各15回/月 |
| 添削問題(国、算) | 15分 | 各1回/月 |
| 経験学習 | 2時間 | 1回/月 |
| 経験学習提出シート | 表記なし | 1回/月 |
| 英語 | 5分 | 3回/月 |
| プログラミング | 15分 | 4回/年 |
| みらい思考力ワーク (オプション講座) | 15分 | 4回/月 |
| みらい思考力デジタル問題 (オプション講座) | 15分 | 4回/年 |
小学生タブレットコース
【1日の学習時間】 約15分
| 教材 | 1回学習量(目安時間) | 回数 |
| 国語、算数 | 15分 | 各8回/月 |
| まとめテスト(国、算) | 15分 | 各1回/月 |
| プラス学習(国、算) | 15分 | 各3回/月 |
| みらいたんけん学習 | 15分 | 2回/月 |
| 英語 | 5分 | 3回/月 |
| プログラミング | 15分 | 4回/年 |
小学生コースとは異なり、提出課題がある訳ではありません。その代わりに、タブレット上でまとめテストを行います。プラス学習はまとめテストの結果に合わせて、応用問題か標準問題が自動で出題されます。
2年生の学習量
小学生コース
【1日の学習時間目安】 約25分
| 教材 | 1回学習量(目安時間) | 回数 |
| メインテキスト(国、算) | 10分 | 各12回/月 |
| ドリル(国、算) | 5分 | 各20回/月 |
| 添削問題(国、算) | 20分 | 各1回/月 |
| 経験学習 | 2時間 | 1回/月 |
| 経験学習提出シート | 表記なし | 1回/月 |
| 英語 | 5分 | 3回/月 |
| プログラミング | 15分 | 4回/年 |
| みらい思考力ワーク (オプション講座) | 15分 | 4回/月 |
| みらい思考力デジタル問題 (オプション講座) | 15分 | 4回/年 |
小学生タブレットコース
【1日の学習時間目安】 約15分
| 教材 | 1回学習量(目安時間) | 回数 |
| 国語、算数 | 15分 | 各8回/月 |
| まとめテスト(国、算) | 15分 | 各1回/月 |
| プラス学習(国、算) | 15分 | 各3回/月 |
| みらいたんけん学習 | 15分 | 2回/月 |
| 英語 | 5分 | 3回/月 |
| プログラミング | 15分 | 4回/年 |
公式サイトをみると、2年生も学習量は1年生と同じようですね。学習量は小学生コースの方が多いのではないでしょうか。
3・4年生の学習量
小学生コース
【1日の学習時間目安】 約30分~40分
| 教材 | 1回学習量(目安時間) | 学習回数 |
| メインテキスト | 国、算、社、理 各30分 英 15分 | 国 5回/月 算 6回/月 理・社 3回/月 英 4回/月 |
| 添削問題 | 国、算、社、理 各30分 英 15分 | 各1回/月 |
| プログラミング | 15分 | 4回/年 |
| 【専科】思考・表現力 (テキスト) | 20分 | 3回/月 |
| 【専科】思考・表現力 (提出課題) | 20分 | 1回/月 |
小学生タブレットコース
【1日の学習時間目安】 約20分
| 教材 | 1回学習量(目安時間) | 回数 |
| 要点・確認問題・練習問題 | 20分 | 国・算 5回/月 理・社 3回/月 英 2回/月 未来 1回/月 |
| ステップ問題(未来を除く) | 10分 | 1回/月 |
| 提出課題(未来を除く) | 15分 | 1回 |
| プログラミング | 15分 | 4回/年 |
| 【専科】思考・表現力 (テキスト) | 20分 | 3回/月 |
| 【専科】思考・表現力 (提出課題) | 20分 | 1回/月 |
5・6年生の学習量
小学生コース
【1日の学習時間目安】 約30~40分
| 教材 | 学習量(目安時間) | 回数 |
| メインテキスト | 国、算、社、理、各40分 英 20分 オンラインスピーキング 25分 | 国 5回/月 算 6回/月 理・社 4回/月 英 7回/月 オンライン 1回/月 |
| 添削問題 | 国、算、社、理、英 各40分 | 各1回/月 |
| プログラミング | 15分 | 4回/年 |
| 【専科】作文(5・6年生) | テキスト・提出課題 各40分 | テキスト 3回/月 提出課題 1回/月 |
| 【専科】公立中高一貫校 適性検査(5・6年生) | テキスト 40分 提出課題 5年生30分、6年生25分 | テキスト 5年生2~3回/月、6年生4回/月 提出課題 5年生1回/月、6年生2回/月 |
| 【専科】公立中高一貫 作文(6年生) | テキスト 40分 提出課題 50分 | テキスト 2回/月 提出課題 1回 |
小学生タブレットコース
【1日の学習時間目安】 約30~40分
| 教材 | 学習量(目安時間) | 回数 |
| 要点・確認問題・練習問題 | 30分 | 国・算 5回/月 理・社・英 3回/月 未来 1回/月 |
| ステップ問題(未来を除く) | 15分 | 1回/月 |
| 提出問題(未来を除く) | 20分 | 1回/月 |
| プログラミング | 15分 | 4回/年 |
| 【専科】作文(5・6年生) | テキスト・提出課題 各40分 | テキスト 3回/月 提出課題 1回/月 |
| 【専科】公立中高一貫校 適性検査(5・6年生) | テキスト 40分 提出課題 5年生30分、6年生25分 | テキスト 5年生2~3回/月、6年生4回/月 提出課題 5年生1回/月、6年生2回/月 |
| 【専科】公立中高一貫 作文(6年生) | テキスト 40分 提出課題 50分 | テキスト 2回/月 提出課題 1回 |
中学受験をするなら小学生コースでOK?
Z会の小学生コースおよびタブレットコースは、教科書よりもハイレベルな学習をおこなっています。しかしながら、中学受験を目指すとなると上記のコースだけで対応するには難しいといえるでしょう。
Z会の中学受験対策には2つの選択肢があります。一つは国立や私立の難関校を目指す場合。そしてもう一つが公立中高一貫校を目指す選択肢です。
それぞれについてZ会では、以下の2つの対策が用意されています。
難関国私立受験を目指す
難関と言われる国立や私立の中学校を目指す場合は、3年生から6年生向けに中学受験コースが良いでしょう。
このコースでは、トータル指導プランと要点集中プランという2つの学習スタイルを選ぶことができます。Z会のみで合格を目指す場合は前者を、塾に通いながら苦手科目などを補強したい場合などに校舎を選びます。
対象校ごとのレベル設定も可能で、最難関レベルと難関レベルを選択することも可能です。
国私立校を志望される場合は、小学生コースではなく中学受験コースを選ばれると良いでしょう。
Z会中学受験コースのページはこちら
公立中高一貫校を目指す
中学受験の選択肢としては、公立中高一貫校を目指すという道もあります。
国私立受験とは異なり、「適性検査」という検定によって合否が判定されます。単に知識を問われるものではなく、複数教科の横断的な知識、そしてそれらを運用する力、思考力や論述力などが求められるのが特徴です。
つまり公立中高一貫校の合格を目指す上では、適性検査に特化した対策が必要となります。
そして、Z会では公立中高一貫校対策の講座も準備されています。
- 公立中高一貫校 適性検査(5,6年生)
- 公立中高一貫校 作文(6年生)
適性検査講座は、現在私の娘も受講していますが、一癖ある問題が多く、解くのに苦労しています。。。ただし、公立中高一貫校を目指す場合は、適性検査の対策だけを行えば良いというものでもありません。基本的な学力の土台が出来上がっているかどうかが非常にカギとなります。
その点を踏まえると、小学生コースまたは小学生タブレットコースと公立中高一貫校受検対策講座の両方を受講される方が良いでしょう。
Z会で公立中高一貫校を目指す方法としては、過去記事にもまとめていますのでこちらもご参考ください。
小学生コース、小学生タブレットコースの口コミは?
小学生コース受講者の声
まず小学生コースの口コミを集めてみました。
確かに難しい問題もありますが、すべての問題が難しいわけではありません。受講していてとくに力の伸びを実感しているのは国語です。Z会では教科書とは違う文章が出題されるので、読解力がみるみる伸びていきました。
引用:Z会
以前別の通信教材をためてしまったことがあり、Z会を始める前は「また同じようになるのでは…」と不安もありました。しかし、いざ始めてみると、問題が手ごたえのある難度になったことで楽しくなり、さらに学習カレンダーで見通しを立てられることで取り組みやすくなりました。
引用:Z会
Z会の受講を決めたポイントは、教材がシンプルである事。あれもこれもと冊数や課題が多すぎると複雑になりますが、Z会なら余計な付録などがなく、教材の紙面や情報がシンプル。そのおかげで、子どもひとりでも教材を管理できるんです。教材の質が良いだけで子どもは取り組みやすいですし、さらに解説がほかの教材と比べて圧倒的にわかりやすいので、すすんで学習できますよ。
引用:Z会
不要なおもちゃやゲームがないところがいいです。
引用:塾ナビ
タブレット学習だと、どのような問題をやっているのか、子どもの回答はどんなだったのかが見れないので、そこをみれるようにしてもらいたい。紙学習でもタブレットの解説動画などを見れるようにしてほしい。
タブレット、紙それぞれのよさをドッキングしたようなコースがあるといい。

シンプルで付録が無い点を評価されている意見は他にも多数ありました。難易度に関しては、やはり個人差があるので評価は分かれているようですね。
まずはお試し教材などでお子さんの反応を見るのも一つでしょう!
小学生タブレットコース受講者の声
受講前は、レベルが高いのではないかという心配がありました。実際受講してみて、「難しい」と言うことはありますが、タブレットで説明してくれるので、基礎・応用は一人できちんと理解して進められています。
引用:Z会
通信教育は飽きるのではないかと不安を感じていたのですが、Z会はいろんなアプローチで子どもを引きつけてくれる内容でした。1回分の時間がそこまで長くないので負担にはならず、しっかり提出課題もあるので、子どもだけでメリハリをつけて学習を進められています。
引用:Z会
子供が通信教育を始めたら、学校の授業が簡単になったと言っていた。先取りで勉強することで学校の授業と合わせて、より理解が深まっていると感じる。
タブレットということもあり、本人は紙より取り組みやすい。タブレットの難点は、問題を間違えても答えが出てきて、理解してないのに直して終わりにしてしまうことができる。紙でもそうだが、そこは人が介在しない学習だと自主性が大事になるが、そこが悩ましい。
引用:塾ナビ

タブレットの方が一人で取り組みやすい点はあるかもしれませんね。学習時間も短く感じるという声もありました。
教材は紙とタブレットのどっちを選ぶべき
2つのコースの比較
上記の口コミで、紙教材とタブレット教材の口コミも載せましたが、どちらを選ぶべきかを悩む親御さんも多いのではないでしょうか。
個人的な観点から比較をしてみました。あくまで小学生コースと小学生タブレットコースとの比較になります。
| 小学生コース(紙教材) | 小学生タブレットコース | |
| 学習時間 | 長 | 短 |
| 費用 | 高い | 安い |
| 個人的感想 | 教材が溜まるので整理が大変 学習状況の把握は自分で確認 目に優しい 紙に書くことは、脳への刺激が良い可能性 | 教材が溜まらない 学習状況がアプリで把握できる 目の負担がかかる タッチペンの感度が不安定な可能性あり |
上記はあくまで個人的感想です。タブレットの方がサクサクと学習が進むので、学習時間は短くなるでしょう。費用に関してもタブレットの方がコスパが良いとは言えます。
紙教材のデメリットの一つは、教材が溜まるので整理が大変という点ではないでしょうか。これは私の妻(無駄なものはバンバン捨てたい派)もよく言っていますが、ちゃんと管理しないとあっという間に散らかってしまいます。
しっかりファイリングするなどの工夫は必要になりますね。その点タブレットは、全ての教材がデバイスの中にある訳ですので、無駄なものが増えません。

ただ、個人的には紙教材が溜まることで、今まで積み重ねてきたことを視覚化できるという点はメリットとも考えています。
学習状況は、タブレットの場合は日々の学習状況がアプリで配信されるので、どれくらいやったかなどはざっくりと把握できます。しかし、どういった問題でつまづいたかなど細かくは分かりません。
紙教材では、添削問題の結果はアプリ内で確認できますが、日々の学習状況は記録が残りません。ですから、どれくらいやったかなどは親が自ら把握する必要があります。一方で、タブレットよりもどういったことを学んでいるのか、何でつまづいているのかなどを確認できる点はメリットとも言えます。

十分にお子さんの学習をサポートする時間が取れる方は、紙教材の方が良いと思いますよ。
最後に、目の負担や紙に書く事による脳刺激などは、個人的には大切な事かなと思っています。私としては、今後いやでもデジタル端末を使用する機会は増えてくるので、小学生の間はなるべく紙教材で行う方が良いという考えです。
この辺りは親御さんの考え方の違いもあると思いますので、紙とタブレットのメリット・デメリットを歯博した上で選択することをおすすめします。
我が家は紙教材を選択
ちなみに私の娘は紙教材を選びました。上述した紙教材とタブレット教材のメリット・デメリットもありますが、一番の理由は、以前別のタブレット教材(スマイルゼミ)で上手くいかなかった経験があったからです。
タブレットは自動解答機能があるため、スムーズに学習を進められる点はメリットです。一方で深く考える前に答えが表示されてしまうことで、何となく分かってしまった気になることもありました。
過去記事に娘が紙教材を選んだ理由についても述べている記事がありますので、こちらも是非参考にしてみて下さい。
まとめ
今回は、数ある通信教育教材の中でも、高い評価を受けているZ会の小学生コースについてまとめてみました。
Z会は「良問ぞろいの質の高い教材」、「丁寧な添削指導」、「自発的な学びにつながる工夫」「付録などがなく学習に集中できる」などが特徴と挙げられます。
小学生向けのコースには
- 小学生コース(紙教材)
- 小学生タブレットコース
- 中学受験コース
があります。
国私立の中学受験を目指すわけではないけど、教科書+αの学力をつけさせたい方にとっては、よい選択肢と言えるでしょう。
また、私の娘もそうですが、公立中高一貫校を目指す方にとっても小学生コースや小学生タブレットコースは学力の基礎をつける上で有効です。そして、目的別講座の公立中高一貫校の受検対策講座を受講するのがオススメです。
お子さんの性格や学力によってもZ会が合うかどうかは分かれると思います。Z会では資料請求を行うとお試し教材がついてきますので、迷っている方は一度テキストをお子さんに試してみるのも良いですよ。
ぜひお子さんにとって最善の学びを提供されることを願っております。