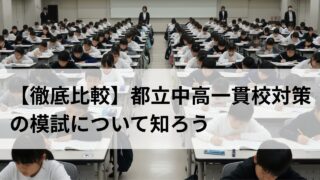「都立中高一貫校が人気みたいだけど、準備って何から始めればいいの?」
「塾に通わせたいけど、費用が心配…」
「通信教育だけでも大丈夫かしら?」
例年、高い人気を誇る都立中高一貫校。その受検対策は小学4年生、5年生といった早期から始めるご家庭も多く、保護者の皆様にとっては学習方法の選択と、それに伴う費用が大きな関心事ではないでしょうか。
特に、都立や公立中高一貫校の受検対策塾の中でも代表格であるenaと、質の高い教材で定評のある通信教育のZ会は、多くの方が比較検討される選択肢の一つかと思います。
実際のところ、通塾と通信教育では、受検本番までの総費用にどの程度の差が出るのでしょうか?

記事に入る前に簡単な自己紹介です。私の娘は都立中高一貫校を目指す2027年組。娘をサポートするために、日々様々な受検情報を収集しています(詳しいプロフィールはこちら)。
さて、私自身も娘の受検対策をする上で通塾や通信教育の費用について調べる必要がありました。
この記事では
- Z会のみで対策を進めるケース
- enaのみで対策を進めるケース
- 小学5年生はZ会、その後enaに切り替えるケース
上記3つのパターンで受検対策を行った場合に、小学5年生から小学6年生の受検直前までの約2年間の費用を具体的に算出し、比較検証してみました。
※enaには集団と個別指導がありますが、今回の記事では集団を選んだ場合の金額で計算しています。
最初に結論から言います。
Z会のみ・・・約27.5万円
enaのみ・・・約133.4万円
Z会×ena・・・約81.8万円
なお、上記の金額は夏期講習などの特別講習費用や模擬試験、その他にかかる費用を除いた金額です。
実際にはこれ以上かかると想定されますが、一つの目安にはなるはずです。
なお、我が家の場合はどのようにしたかというと
このような決断をしました。
費用だけでなく、それぞれのメリットや注意点についても軽く触れていきますので、お子様に合った学習方法を選ぶ上での参考にしていただければ幸いです。
期間限定で特典プレゼント
2026年2月27(金)〆切
本記事の費用比較における前提条件
具体的な費用を見ていく前に、今回の比較における前提条件を明確にしておきます。より正確な比較のために、いくつかのルールを設定しました。
1. 対象期間: 今回の費用算出の対象期間は、小学5年生から小学6年生とします。
ただし、Z会の公立中高一貫校受検対策は、教材が届く小学5年生の4月~小学6年生の12月までの21か月間で算出します。
一方、enaは2月が新年度の始まりとなりますので、小学4年生の2月から受検直前となる小学6年生1月までの24か月間で算出します。
Z会よりもenaの方が対策期間は3か月分長く算出しておりますが、約2年間の学習計画にかかる費用としてこの期間にしましたので、その点はご理解ください。
2. 費用に含むもの・含まないもの:
費用に含むもの
- 小学5年生・6年生の本科コース(4教科:国算理社)の月額受講料(12ヶ月一括払いの場合の月額を基準)
- 専科 公立中高一貫校適性検査講座(5年生・6年生)の月額受講料(12ヶ月一括払いの場合の月額を基準)
- 専科 公立中高一貫受検対策作文講座(6年生)の月額受講料(12ヶ月一括払いの場合の月額を基準)
費用に含まないもの
- オプション講座、外部模試の費用、教材以外の学習サポート費用
費用に含むもの
- 入塾金
- 小学5年生・6年生 都立コースの月額授業料
- 模試教材費(前期・後期)
費用に含まないもの
- 8月授業料、春期講習、夏期講習、冬期講習、正月特訓などの特別講習費、合宿費、オプション講座費用、一部の特別模試費用など。
これらの前提条件をご理解いただいた上で、具体的な費用比較を見ていきましょう。
Z会、ena共に2025年6月時点で公式HPに掲載されている金額で算出しております。若干の誤差が生じるケースもありますので、正確な費用に関してはお問い合わせの上ご確認ください。
【通信教育】Z会のみで都立中受検を目指す場合の費用
まずは、通信教育の雄であるZ会の教材のみを利用して、都立中高一貫校受検対策を行う場合の費用を見ていきます。Z会は、自宅で自分のペースで学習を進めたいお子さんや、通塾が難しいご家庭にとって魅力的な選択肢です。
算出期間:小学5年生4月~小学6年生12月
- 小学生コース4教科: 8,364円/月(12ヶ月一括払いの場合)
- 専科 適性検査講座 5年生: 3,145円/月(12ヶ月一括払いの場合)
- 5年生の年間合計: (8,364円 + 3,145円) × 12ヶ月 = 11,509円 × 12ヶ月 = 138,108円
- 【本科】 小学生コース4教科: 8,364円/月(12ヶ月一括払いの場合)
- 【専科】 適性検査講座 6年生: 3,400円/月(12ヶ月一括払いの場合)
- 【専科】 公立中高一貫受検対策作文講座 6年生: 3,400円/月(12ヶ月一括払いの場合)
- 6年生の合計(9ヶ月分): (8,364円 + 3,400円 + 3,400円) × 9ヶ月 = 15,164円 × 9ヶ月 = 136,476円
※Z会の受講費用は12か月払い、6か月払い、毎月払いとがあり、月額料金が異なりますのでご注意ください。
Z会のみの場合の総費用(約2年間):
138,108(5年生) + 136,476円(6年生) = 274,584円
Z会のみで対策を行う場合、2年間の総費用は約27.5万円となりました。後述する通塾のケースと比較すると、費用を大幅に抑えられることがわかります。
ただし、上記はZ会のテキストのみを受講した場合の料金です。
ここに模試受検費用や塾の短期講習、その他市販教材などの購入費用があれば、さらに金額は増えていきます。

Z回のみで受講するメリットは何と言っても「学習の自由度」。自宅で好きな時間に学習ができるので、親が送迎する必要もありません。また、習い事を継続したいお子さんにとっても良い選択と言えるでしょう。そしてZ会の教材は良問が厳選されているとの評判で、通塾よりも費用を抑えつつ学習できるのはも高く評価できます!

一方で注意点は、自己管理能力があるかどうか。やはり子どもだけでは難しい部分も多いので、親のサポートも重要になりそう。あとは塾とは違って先生にすぐ質問できない点や、競争相手が目の前にいないこともモチベーションに影響するかも。。。
Z会のみで合格を目指すには、お子さんの性格や学習スタイル、そしてご家庭のサポート体制が非常に重要になると言えるでしょう。
【通塾】enaのみで都立中高一貫校受検を目指す場合の費用
次に関東圏、特に東京都内において都立中高一貫校受検指導で高い実績を誇るenaに、小学4年生2月から受検直前まで通塾した場合の費用を見ていきます。
enaは、独自のカリキュラムと豊富な情報量、そして切磋琢磨できる環境が魅力です。
算出期間:小学4年生2月~小学6年生1月
- 月額授業料: 44,600円
- 模試教材費(小5):
- 前期分(2月〜7月):76,560円
- 後期分(9月〜1月):63,800円
- 新小5期間の合計: 44,600円 × 1Ⅰヶ月 + 76,560円 + 63,800円 = 490,600円+ 76,560円 + 63,800円 = 630,960円
- 月額授業料: 50,600円
- 模試教材費:
- 前期(2月~7月):79,860円
- 後期(9月~3月):66,550円
- 6年生の合計(通常費用): 50,600円 × 11ヶ月 + 79,860円 + 66,550円 = 556,600円 + 79,860円 +66,550円 = 703,010円
enaのみの場合の総費用(約2年間): 630,960円(小5)+703,010円(小6)=1,333,970円
enaのみで対策を行う場合、2年間の総費用は約133.4万円となりました。Z会のみのケースと比較すると約107万円の差があり、やはり通塾には相応の費用がかかることが分かります。
ただし、前述の通り、ここには季節講習などの特別講習費は含まれていません。これらを含めると、費用はさらに大きく膨らむ可能性があります。

enaのメリットは何と言って都立中入試の高い合格実績。合格者数の50~75%(※)がenaを利用しているらしいです。都立中に関するノウハウや対策は充実していると言えるでしょう。また、競争環境によるモチベーション維持や質問できる環境、定期的な模試で実践練習がつめるのもポイントです!
(※)10時間以上指導をenaで受けた生徒をカウントされているので、短期講習のみのお子さんも含むと思われます。

デメリットはやはり費用面ですね。。。2年間で133万円はあくまで最低限で、夏季講習などの特別講習費も大きな負担になりそうです。また、演習量や宿題なども多くなるので、精神面で子供が追い込まれる可能性もあります。習い事なども制限しなくてはいけないでしょう。
enaに通うことは、質の高い指導と刺激的な環境を得られる一方で、費用面や時間的な拘束が大きい点を理解しておく必要があります。
【組み合わせ】Z会(通信教育)からena(通塾)へ切り替える場合の都立中高一貫校受検費用
最後に、小学5年生の間はZ会で基礎固めと学習習慣の定着を図り、受検学年となる小学6年生からenaの都立コースに切り替える、というパターンの費用を見ていきましょう(小学5年生の2月が新年度)。
この方法は、それぞれの学習スタイルの良いとこ取りを狙う戦略と言えます。
算出期間:Z会(小学5年生4月~1月:10ヶ月間) → ena(小学5年生2月~小学6年生1月:12ヶ月間)
- 小学生コース4教科: 8,364円/月
- 専科 適性検査講座 5年生: 3,145円/月
- Z会 5年生合計(10ヶ月分): (8,364円 + 3,145円) × 10ヶ月 = 11,509円 × 10ヶ月 = 115,090円
- 月額授業料: 50,600円
- 模試教材費:
- 前期(2月~7月):79,860円
- 後期(9月~3月):66,550円
- 6年生の合計(通常費用): 50,600円 × 11ヶ月 + 79,860円 + 66,550円 = 556,600円 + 79,860円 +66,550円 = 703,010円
Z会 → ena 切り替えパターンの総費用: 115,090(Z会) + 703,010円(ena) = 818,100円
Z会で10ヶ月間学習した後、enaに切り替えるパターンの総費用は約81.8万円となりました。

2年間通塾するよりも費用を抑えつつ、本格的な受検年度に集中的に塾で指導を受けられるのは良い考えかもですね。都立中受検の特異性から、長期の通塾が必ずしも合格率アップにつながらないという意見もあります。基礎固めをZ会で行い、最終学年で一気に実践的な演習量を増やす一つの戦略と言えそう。

ただ、5年生からみっちりと通塾している子はペースをつかんでいるので、それに対して焦ってしまう可能性があるかも。通信教育で自分のリズムでやっていた子にとっては、塾のスピードに適応できるかどうかがカギですね。
この組み合わせパターンは、費用と学習効果のバランスを取りたいと考えるご家庭にとって、魅力的な選択肢の一つと言えるでしょう。
ただし、切り替えのタイミングや、お子さんの適応力などを慎重に考慮する必要があります。
受検対策プランの費用比較と追加費用など

受検対策プランごとの費用面に関する比較
ここまでの3つのパターンの費用をまとめて比較してみましょう。
- Z会のみが最も低コスト(約27.5万円): やはり通信教育であるZ会のみで進めるのが、費用面では圧倒的に有利です。通塾のみであれば1/5程度、Z会から通塾パターンであれば1/3程度の費用で済みます。
- enaのみは高コストだが手厚いサポート(約133.4万円): enaのみの場合は、専門的な指導や環境維持のために相応の費用がかかります。ただし、これには基本的な模試費用や教材費が含まれており、手厚いサポートが期待できます。
- Z会⇒enaは中間的な費用(約81.8万円): Z会からenaへ切り替えるパターンは、両者の中間的な費用となり、enaに最初から通うよりも約56万円は費用を抑えられる計算です。
追加費用を考慮する
本記事ではZ会のみ、enaのみ、そしてZ会からenaの3パターンで基本的な費用のみを算出してきました。
ただ、実際には追加費用もかかってきます。
- Z会、enaともに塾の短期講習や直前合宿など参加する場合の特別費用
- 通塾しながら演習量を増やすために、Z会の専科のみを受講
- 公立中高一貫校受検模試の受験費用
- Z会の5年生で受講できる作文講座の受講(公立中高一貫校の直接的な対策講座ではない)
- 通信教育、通塾開始が途中からとなる場合
- 市販教材の購入費用
特に塾の特別費用はかなり高額になる可能性があります。
どの程度受講するかによっても変わりますが、基本料金から数十万はかかるということを頭に入れておかなくてはいけません。
都立中高一貫校受検の学習方法を選ぶポイント(通塾 vs 通信教育)
ここまで費用面を中心に比較してきましたが、都立中高一貫校受検の学習方法を選ぶ際には、費用以外にも考慮すべき重要なポイントがたくさんあります。
最終的には、お子さんの性格や学習スタイル、ご家庭の教育方針やライフスタイルに最も合った方法を選ぶことが、合格への近道となるでしょう。
1. 子どもの性格・学習スタイル
- マイペースで探求心が強いタイプか、競争環境で伸びるタイプか:
- 自分のペースでじっくり取り組みたいお子さんや、興味のあることを深く掘り下げたいお子さんには、Z会のような通信教育が向いているかもしれません。
- 一方で、周りにライバルがいて、競い合うことでモチベーションが上がるお子さんや、先生に直接教えてもらう方が理解しやすいお子さんには、enaのような通塾が適しているでしょう。
- 自己管理能力の程度:
- 計画的にコツコツと学習を進められるお子さんであれば、通信教育でも成果を出しやすいです。
- 学習計画を立てたり、誘惑を断ち切って勉強に取り組んだりするのが苦手なお子さんの場合は、塾のスケジュールや宿題といった強制力があった方が学習が進むかもしれません。
- 質問の頻度や解決方法:
- 疑問点をすぐに解決したい、先生に直接質問したいというお子さんには、通塾が安心です。
- 自分で調べたり、少し時間をかけて考えたりすることが苦にならないお子さんであれば、通信教育の質問サービスでも対応できる場合があります。
2. ご家庭の教育方針・サポート体制
- 家庭学習への関与度:
- 通信教育を選択する場合、保護者の方の学習計画のサポート、進捗管理、丸付け、精神的な励ましなどがより重要になります。共働きなどで時間に余裕がないご家庭にとっては、負担が大きいと感じるかもしれません。
- 通塾の場合でも家庭学習は必須ですが、学習内容や進捗管理の多くを塾に任せられるという側面もあります。
- 送迎の可否:
- 塾に通う場合、特に低学年のうちは送迎が必要になることが多いです。お仕事や下のお子さんの都合で送迎が難しい場合は、通信教育やオンライン指導などが現実的な選択肢となります。
- 情報収集力:
- 塾は最新の入試情報や学校情報を提供してくれますが、通信教育の場合は保護者自身がアンテナを高くして情報収集を行う必要があります。説明会への参加や、インターネット、書籍などを活用する積極性が求められます。
- 費用に対する考え方:
- 教育費にどれくらい予算を割けるかは、ご家庭によって異なります。無理のない範囲で、かつお子さんにとって最適な学習環境を選んであげることが大切です。
3. 学習環境
- 静かに集中できる学習スペースの確保: 自宅学習が中心となる通信教育では、お子さんが集中して勉強に取り組める環境を整えることが重要です。
- 学習時間と他の活動とのバランス: 受検勉強だけでなく、学校生活、習い事、遊び、睡眠時間なども大切です。通塾に時間がかかると、これらのバランスが崩れてしまう可能性もあります。お子さんの生活全体を見渡して、無理のない計画を立てましょう。
4. 受検までの残り期間や現在の学力
- 受検までの残り時間が少ない場合や、基礎学力に不安がある場合は、集中的に指導を受けられる塾の方が効率的な場合もあります。
- 逆に、早期から準備を始める場合は、まずは通信教育でじっくりと基礎を固め、必要に応じて塾の講習を利用したり、高学年から通塾に切り替えたりするのも良いでしょう。
これらの要素を総合的に考慮し、お子さんとよく話し合って、納得のいく学習方法を選択することが何よりも重要です。
途中で学習方法を見直すことも、もちろん可能ですのでその都度検討していくと良いでしょう。
我が家の場合:まずはZ会⇒今後は塾の活用もあり
参考までに私の家庭の状況をお話しします。
小学5年生の4月から都立受検対策を始める事になりましたが、まずはZ会の通信教育から始める事にしました。
ちなみenaは自宅から徒歩で通塾できるエリアには住んでいます。
私の娘がZ会で受講するコースは以下の通りです。
それぞれ12か月払いで申し込みました。
Z会から始めることにした主な理由は以下の通りです。
- 2年間の通塾にかかる経済的負担の大きさと費用対効果
- Z会の実績や良質な教材に魅力
- 習い事を継続したい
- 自主学習の習慣がついている
- 塾の活用は状況に応じて検討すれば良い
我が家にとっては最初からの通塾は適していないと考えました。
ただし、受検直前までZ会のみでやることに決めたわけではありません。状況によっては塾も併用したいとは考えています。
- 早い段階で通信教育から通塾に切り替える
- 夏期講習などの特別講習のみを利用
- 塾が主催している模試を受ける
塾におんぶにだっこではなく、必要であれば積極的に活用するというスタンスでいたいと思います。
なお、Z会を最初の受検対策として選んだ経緯は、受検日記にもまとめていますので、興味のある方はこちらもご覧ください。
まとめ:家庭に合った都立中高一貫校受検の準備を
今回は、都立中高一貫校受検対策として人気の高いena(通塾)とZ会(通信教育)について、小学5年生からの約2年間の費用を3つのパターンで比較検証しました。
- Z会のみ:約27.5万円
- enaのみ:約133.4万円
- Z会(小5)→ena(小5の2月~):約81.8万円
やはり、費用面では通信教育であるZ会に大きなアドバンテージがある一方で、enaのような通塾には専門的な指導や豊富な情報、切磋琢磨できる環境といった魅力があります。
そして、両者を組み合わせることで、費用を抑えつつ、必要な時期に専門的なサポートを受けるという選択肢も見えてきました。

ただし、何度もいいますが、今回の費用比較は「基本的な月謝と教材費」に基づいた概算となります。
特に通塾の場合は、短期講習や直前対策講座などの高額な特別講習費が別途必要になることが一般的で、これらを含めると総費用はさらに上がります。
追加費用は、どの程度特別講座を受けるかにもよりますが、50~80万円前後はかかるという声もあります。
また、Z会の場合も、外部模試の受験費用や、必要に応じて市販の教材を追加購入する費用なども考慮しておくと良いでしょう。
まずは「だいたいこの位はお金がかかるんだな」というのが、押させておければ良いと思います。
その上で、最終的にどの受検対策を選ぶかは、お子さんの性格や学習スタイル、ご家庭の教育方針やライフスタイルが決め手になるはずです。
悔いのない受検対策を立てる為にも、様々な角度からベストな選択を模索していければ良いですね。
この記事が、皆様の都立中高一貫校受検準備の一助となれば幸いです。
私にも言える事ですが、子どもが目標に向かって積極的に学習に取り組めるよう、最適なサポート方法を見つけていきましょう。
期間限定で特典プレゼント
2026年2月27(金)〆切