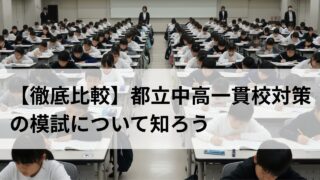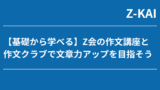公立中高一貫校の受検を考えているけれど、「作文が苦手で対策に困っている…」というご家庭は多いのではないでしょうか。
適性検査型の問題では、思考力や表現力が問われるため、作文は合否を分ける重要な科目です。しかし、家庭学習だけではなかなか対策が難しいのも事実。
そこで今回は、質の高い添削指導で定評のあるZ会の公立中高一貫校対策講座の中から、特に「作文」に特化した講座「公立中高一貫校 作文」を深掘りして解説します。
この記事を読めば、Z会の作文講座の特徴から、お子さんに合ったコースの選び方まで、すべてが分かります。ぜひ、作文対策の参考にしてください。
期間限定で特典プレゼント
2026年2月27(金)〆切
なぜ公立中高一貫校受検で作文が重要か
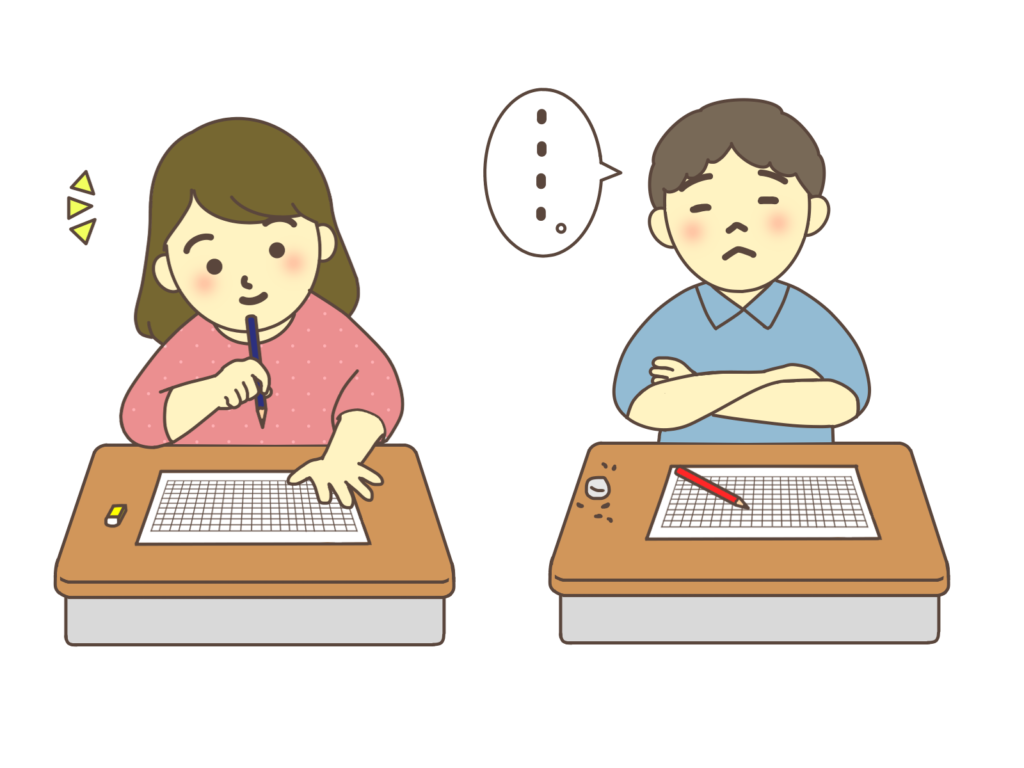
そもそも、なぜ公立中高一貫校の受検で「作文」がこれほどまでに重視されるのでしょうか。
都立中受検は作文問題が必須
東京都の公立中高一貫校(都立中)の受検では、「適性検査」が実施されます。この適性検査は、国語・算数・理科・社会といった教科の枠を超えた横断的な問題で構成されており、知識だけでなく思考力が問われます。その中で、400字〜600字程度の本格的な作文問題が必須となっているほか、資料の読み解きや自分の考えを短く記述する問題も数多く出題されます。
これは、単に文章を書く能力だけでなく、
- 課題文や資料を正確に読み解く読解力
- 自分の考えを論理的に組み立てる構成力
- 具体的な経験や知識を交えて説得力を持たせる表現力
といった総合的な力が問われるためです。作文の配点も決して低くなく、ここで確実に得点できるかどうかが、合格を大きく左右します。
また、この傾向は都立中に限りません。神奈川県、千葉県、埼玉県をはじめ、全国の多くの公立中高一貫校の適性検査で、作文や記述問題が出題されています。 公立中高一貫校を目指すなら、作文対策は避けて通れない道なのです。
都立中受検の作文問題の出題傾向
都立中の作文問題は、学校によって特色がありますが、主に以下のような傾向が見られます。
- 資料読解型: 文章やグラフ、写真などの資料を読み解き、それに基づいて自分の考えを述べる形式。
- テーマ型: 与られたテーマについて、自分の経験や知識を基に意見を述べる形式。
- 課題解決型: 問題点や課題が提示され、その解決策を論理的に説明する形式。
いずれの形式でも、「自分の考えを、理由や具体例を挙げて分かりやすく伝える力」が共通して求められます。付け焼き刃の対策では対応が難しく、早期から継続的にトレーニングを積むことが合格への近道です。
Z会の公立中高一貫 作文講座とは
作文の重要性は分かったけれど、どう対策すれば良いのか分からない…
そんなご家庭におすすめなのが、Z会の「公立中高一貫 作文」講座です。
Z会の公立中高一貫校対策は2本柱
Z会の小学生向けコースには、公立中高一貫校対策として、大きく分けて2つの講座があります。
- 専科「公立中高一貫校 適性検査」: 適性検査で問われる文系・理系の問題をバランスよく学び、総合力を鍛える講座。
- 専科「公立中高一貫校 作文」: 作文に特化し、文章の構成力や表現力を集中的に高める講座。
この2つの講座を組み合わせることで、適性検査対策を万全にすることができます。今回は、特に2つ目の「公立中高一貫校 作文」講座に焦点を当てて解説します。
前回の記事で「公立中高一貫 適性検査」についてまとめていますので、こちらも合わせて読みください。
講座の特徴
Z会の作文講座が多くの受検生から支持される理由は、その特徴的な学習システムにあります。
- 質の高い添削指導: Z会の最大の魅力は、なんといっても添削指導の質の高さです。一人ひとりの答案を丁寧に読み込み、「どこが良かったか」「どうすればもっと良くなるか」を具体的に指導してくれます。的確なアドバイスは、子どものやる気を引き出し、書く力を着実に伸ばします。
- 段階的なカリキュラム: いきなり長文を書かせるのではなく、文章の基本ルールから構成の立て方、表現の工夫まで、スモールステップで学べるように設計されています。無理なく力を伸ばせるので、作文が苦手な子でも安心して取り組めます。
- 良質なオリジナル問題: 実際の入試問題を徹底的に分析して作成されたオリジナル問題は、思考力を刺激する良問ばかり。多様なテーマに触れることで、どんな問題にも対応できる応用力が身につきます。
学習量とカリキュラム
対象は小学6年生で、1年間を通して作文の基礎から応用までを体系的に学びます。
1か月の学習量
1カ月の学習量は、メインテキストが5~9ページで構成されており、学習にかかる目安時間は約40分×2回となります。
また、添削問題にかかる時間の目安が約50分×1回となっています。
カリキュラム
Z会の公式サイトに公立中高一貫校 作文のカリキュラムが掲載されています。
それによると3か月ごとに作文の基礎、発展、そして実践演習へと段階的に取り組んでいく構成となっています。
カリキュラムの詳細は公式サイトをご確認ください→小学生コース専科 公立中高一貫校受検対策講座のご案内
受講費用
受講費用は支払い方法によって異なり、12カ月一括払いの場合は月あたり3,400円、毎月払いの場合は4,000円です。本講座は4月開講、12月終了のカリキュラムとなっています。一括払いを選ぶと、1カ月あたりの受講料が割引になり、よりお得に受講できます。
※途中入会の場合、終了月までの受講期間が7カ月以上12カ月未満の場合は、12か月一括払いの1か月あたりの受講金額×受講月数で請求されます。受講期間が2か月以上6カ月未満の場合は、6か月一括払いの1か月あたりの受講金額×受講月数で請求されます。
※詳細な料金は変更される可能性があるため、公式サイトでご確認ください。
学習の進め方
Z会の学習は、以下のサイクルで進みます。
- テキストで学ぶ: 分かりやすい解説と練習問題で、その月のテーマをインプットします。
- 添削問題に挑戦: 学んだことを活かして、実際に作文を書き、提出します。
- 添削指導を受ける: 専門の添削指導者から、丁寧な赤ペン指導とアドバイスが返却されます。
- 復習する: 添削内容を見直し、自分の弱点を克服します。
このサイクルを繰り返すことで、書く力が定着していきます。
「公立中高一貫校 作文講座」と「作文講座」との違い
Z会には、「公立中高一貫校 作文」講座の他に、小学5・6年生を対象とした「作文」講座も存在します。この2つはどう違うのでしょうか。
「作文」講座の特徴と公立中高一貫作文との違い
2つの講座は、対象学年、目的、内容が明確に異なります。
小学5・6年生向けの「作文」講座は、日常的な文章力の向上や読書感想文など、幅広く「書く力」の土台を作ることを目的としています。そのため、語彙トレーニングや物語の創作といった、楽しく書くことに親しむ内容が中心です。
一方、小学6年生向けの「公立中高一貫校 作文」講座は、適性検査を突破することが目的です。資料の読解や課題解決型の問題など、より実践的で論理的な思考力が求められる内容になっており、まさしく受検に特化した講座と言えます。
「作文講座」は受ける必要はある?
この記事の読者の多くは、公立中高一貫校の合格を目指している方だと思います。結論から言うと、6年生になったら、より実践的な「公立中高一貫校 作文」講座を受講するのが合格への近道です。
では、基礎的な「作文」講座は不要なのでしょうか。
もしお子さんが作文に強い苦手意識を持っているなら、5年生のうちに「作文」講座で基礎を固めておくという戦略が非常に有効です。
- 5年生: まずは「作文」講座で、文章を書くことの楽しさを知り、基礎固めをします。
- 6年生: 土台ができた状態で「公立中高一貫校 作文」講座に切り替え、適性検査に特化した実践力を鍛えます。
このステップを踏むことで、無理なく、しかし着実に合格レベルの作文力を身につけることができます。
公立中高一貫 作文講座のメリット、デメリット
次に、この講座のメリットとデメリットをまとめてみました。
【メリット】
- 段階的に書き方が学べる: カリキュラムが体系化されており、「何から手をつければいいか分からない」という状態からでも、ステップに沿って段階的に作文の書き方を学べます。
- 入試を分析した良質な問題に取り組める: 実際の入試問題を徹底的に分析して作られたオリジナル問題に取り組むことで、多様なテーマに対応できる実践的な力を養うことができます。
- 質の高い添削指導が自宅で受けられる: 送り迎えの必要がなく、自分のペースで学習を進められます。専門の指導者から客観的な視点で評価してもらえるため、親が教えるよりも子どもが素直にアドバイスを受け入れやすい点も魅力です。
- 「書く→添削→書き直し」のサイクルが身につく: このサイクルは、受検だけでなく、中学入学後、さらには社会に出てからも役立つ重要なスキルです。
【デメリット】
- 基礎力がない子には難しい可能性: 受検に特化した内容のため、ある程度の読み書きができることが前提です。作文への苦手意識が非常に強い場合は、先に紹介した5年生向けの「作文講座」などで基礎を固めてからでないと、ついていくのが難しい可能性があります。
- 演習量が不足する可能性: 月に1回の添削問題だけでは、演習量が足りないと感じる子もいるかもしれません。その場合は、市販の問題集などを併用して、とにかく書く機会を増やす工夫が必要です。
- 費用がかかる: 塾に通うよりは安価ですが、市販のテキスト数冊で対策する場合に比べると費用は高くなります。費用対効果を考える必要があります。
- モチベーションの維持: 通信教育全般に言えることですが、家庭での声かけや学習計画の管理など、保護者のサポートが重要になります。
公立中高一貫校 作文の口コミ
Z会の公立中高一貫校 作文講座の口コミを挙げておきます。作文に苦手意識を持っているお子さんも多い印象ですが、この講座を受講したことで克服した受験生も多いようですね。
毎月様々な課題で、とにかく規定文字数を書き上げる訓練を積んだことで、作文への苦手意識が軽減されました。とても丁寧に書き込んで返却してくださる添削のおかげもあり、「ここをもっと膨らませよう」「本番でもこの表現方法は使える」と、文章を書く際のパターンを見つけることができたようです。非常に助けられました。
引用:Z会公式サイト
第一希望も第二希望も合格できて、とても嬉しいです。Z会の作文添削は、毎月継続することで自信がつきました。頑張って良かったです。
引用:Z会公式サイト
まとめ
今回は、Z会の「公立中高一貫校 作文」講座について詳しく解説しました。
適性検査において、作文は受検突破の大きなカギを握っています。配点が高く、対策の有無で大きく差がつくからです。しかし、その対策は独学では非常に難しいのが現実です。
Z会の講座を活用すれば、質の高い添削指導を通じて、合格に必要な思考力・構成力・表現力を着実に身につけることができます。
【この記事のポイント】
- 公立中高一貫校の受検では、思考力や表現力を問う作文が必須。
- Z会の「公立中高一貫校 作文」講座は、質の高い添削指導で実践力を養う。
- 作文が苦手な子は、5年生向けの「作文」講座で土台作りから始めるのがおすすめ。
- 自宅で学習できる手軽さの一方で、継続するための家庭のサポートも大切。
作文は、正しい方法でトレーニングを積めば、誰でも必ず上達します。Z会の力を借りて、苦手を得意に変え、志望校合格を掴み取りましょう。