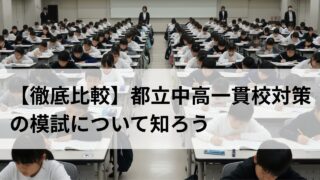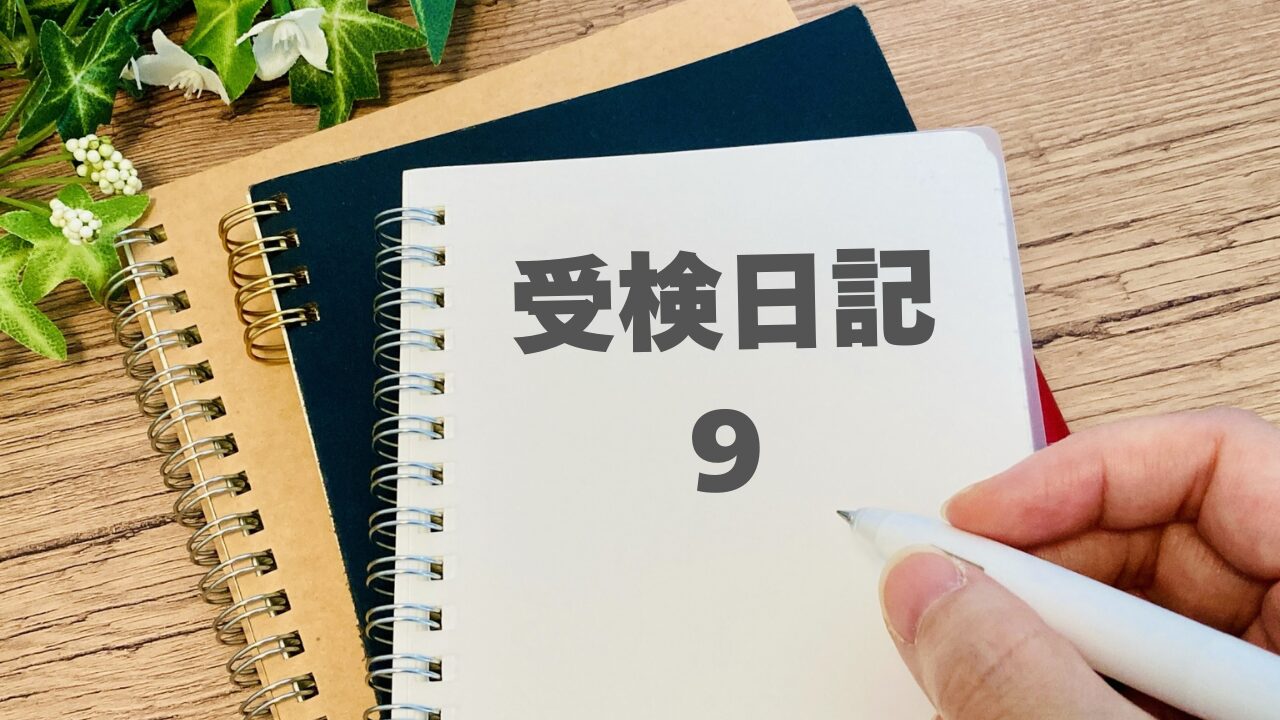こんにちは、よっさんです。
前回の受検日記#8では、娘が受検に対してかなり前向きになってきたお話をしました。
一方で娘に都立中高一貫校受検をさせることに対して、また迷いが出てきたのもこの頃です。
きっかけは妻の一言でした。

ねぇ・・・あの子を本当に受検させるべきなのかなぁ・・・?
今までも色んなことに頑張っているのに、これ以上無理させてしまっていいのかしら?
妻としては、受検勉強をさせることが娘の負担となってしまうのではないか?
親が勝手に盛り上がってしまったけど、本当にそれでいいのだろうかと心配していました。
つまり、中学受験(受検)をさせることは親の自己満足、いわゆる「親のエゴ」ではないのかという懸念です。

確かに娘から「受検したい」と言い出したわけじゃないしなぁ。。。
子どものためにと思って受検をさせることが、必ずしも本人の幸せとはならない可能性もあります。
まだ受検するかどうかを決めていないこのタイミングで、今一度この点について考えるべきだと思ったわけです。
今回はまず「中学受験は親のエゴである」という理由と、「親のエゴを防ぐためのポイント」をまとめてみました。
そして、私たちが受検させることに対して何を心配したのか。
また、それらに対する我が家の受験に対する方針も再確認しました。
結論としては
となりました。
中学受験が「親の受験」にならないために大切なことは何か。
同じようにお悩みの方の参考になれば幸いです。
それでは参りましょう。
受検日記#1から最新話までを一覧表にしています。「最初から読みたい方」「気になる話から読みたい方」は、こちらからどうぞ。
なぜ中学受験は親のエゴと言われる?
そもそも「親のエゴ」とは?
では、中学受験がなぜ親のエゴと言われるのかについて考えていきましょう。
まず、「エゴ」って何でしょう?
エゴの語源はラテン語の「ego=私」となります。
元々エゴは心理学的な用語で「自我」や「自己」を表し、これ自体はフラットな意味です。
ただ、日本語の使われ方としては「自分中心な考え」というマイナスのイメージが強いかもしれません。
つまり、親のエゴとは
と言えます。
中学受験はまだ未熟な小学生の決断だけで行われることはほぼないでしょう。。
だからこそ、高校受験よりも親の意向が強く出やすいのです。
そして、過剰な親の干渉が「親のエゴ」と批判的な意見を受ける理由と言えそうです。

「親の受験」と言われるのもそのためですね!
「親のエゴ」となる理由5選
では、中学受験が親のエゴといわれる主な理由を5つ挙げてみました。
- 親の価値観の押しつけへの懸念
- 競争社会への過剰な適応
- 親自身のコンプレックスの投影
- 子ども主体ではない進路選択
- 経済格差や教育格差の拡大
それぞれもう少し細かく説明していきますね。
⓵親の価値観の押しつけへの懸念
親が「いい中学に入れば将来安泰」「有名校こそ成功への道」といった価値観を持ち、それを子どもに押しつけてしまうケースがあります。
このような場合、子どもの意思や適性が置き去りにされることがあり、周囲から見ると「親の自己満足(エゴ)」と映ることがあります。
②競争社会への過剰な適応
学歴重視の社会で「我が子にいいスタートを切らせたい」と願う親心が、過熱した中学受験へとつながることもあります。
その姿勢が時に過度な詰め込み教育や精神的プレッシャーにつながり、子どもよりも親の思惑が前面に出ているように見える場合があります。
③親自身のコンプレックスの投影
自分が果たせなかった夢や、過去の学歴への劣等感を「子どもにたくす」ケースもあります。
このような動機が中学受験の背景にある場合、それはまさに「親のエゴ」の表れとみなされやすくなります。
④子ども主体ではない進路選択
子どもがまだ10〜12歳という未成熟な段階で受験をすることから、どうしても親主導になりやすいという構造的な事情もあります。
そのため、「子どもの意思ではなく、親の主導で選ばれた道」という印象がつきまといやすいのです。
⑤経済格差や教育格差の拡大
私立中学に進学するには多くの場合、学費や塾代といった経済的な負担が伴います。
このため、「中学受験=富裕層の親のステータス競争」と捉える意見もあり、そこに対する反発や皮肉として「親のエゴだ」という言葉が使われることもあるようです。
親のエゴを防ぐポイント7選
では、親のエゴにならないためには、どのように中学受検と向き合えば良いのでしょうか。
私がWebサイトや書籍を調べて参考になったポイントを7つ挙げてみます。
- 「子どもの気持ち」をくみ取り、意見を尊重する
- 中学受験の適正を見極める
- 情報は親が、意思決定には子どもも参加
- 「進学=ゴール」ではなく「成長のプロセス」ととらえる
- 他者との比較ではなく「わが子基準」で考える
- 子どもの「生活全体のバランス」を見守る
- 第3者の意見も聞く
それぞれもう少し詳しく解説していきますね。
①「子どもの気持ち」をくみ取り、意見を尊重する
中学受験において、最も大切にするべきは子どもの意見を尊重することです。
子どもが受験に興味を持っているか、不安に感じていることはないかなど、様々な事を繰り返し会話の中で確認します。
また、子どもに意見を聞く際にも、いくつか選択肢を与えるのも良いかもしれません。
例えば「AとBだったらどっちの方がいいと思う?」と聞くと答えやすくなるはずです。
さらにいうと、本人がうまく言葉にできなくても、表情・行動・態度からサインを読み取ろうとする姿勢が大切となるでしょう。

しっかりコミュニケーションを取ることが大切ですね!
②中学受験の適正を見極める
親がどれほど中学受験に魅力を感じ、子どもを良い学校に入れたいと願っても、本人に適性が無ければ挑戦させるのは難しいでしょう。
中学受験に適性があるかどうかは、基礎学力や学習習慣、学習への意欲、物事への関心興味、体力、そして精神的な成熟度など、総合的に判断する必要があります。
親の思いだけではなく、客観的な視点から自分の子どもが中学受験を乗り切れるかどうかを見極めましょう。
③情報は親が、意思決定には子どもも参加
学校の特色や受験の仕組み、生活の変化など、受験に関する情報については親が調べなくてはいけません。
そして、それを子供に対してわかりやすく伝えることが大切です。
また、情報は様々な角度から取り入れることが大切で、ある特定の意見だけを取り入れるのは危険です。
そのうえで、「どう思う?」「やってみたい気持ちはある?」と子どもの考えを聞き、一緒に考えるスタイルを作りましょう。
志望校を決める際には、実際に学校見学や文化祭などにいき、本人の気持ちを確認するのも有効ですね。
④「進学=ゴール」ではなく「成長のプロセス」ととらえる
合格・不合格に関係なく、「この経験がこの子の成長につながるか」という視点で判断します。
親の期待を押しつけるのではなく、受験を通じて得られる自信・学び・自己理解に価値を見出します。
もちろん合格することを目標として取り組むのは間違っていません。
しかし、本来の目的は将来的に大きく成長してほしいという気持ちで中学受験を選択したはずです。
合格、不合格にかかわらず、受験に取り組む期間を成長のプロセスと考えるのも一つです。
⑤他者との比較ではなく「わが子基準」で考える
他の家庭やきょうだい、SNSなどと比べて「うちの子も○○すべき」と考えると、無意識にプレッシャーをかけてしまいます。
その子の性格・ペース・興味に合った進路を一番に考えることが、最終的に満足度の高い選択につながります。
中学受験が絶対ではなく、他にも選択肢はあると考えておくのも一つです。
他人軸ではなく自分の子ども軸で受験に臨むことが大切です
⑥子どもの「生活全体のバランス」を見守る
勉強だけでなく、遊び・睡眠・家族との時間・人間関係なども含めた生活の質を大切にする視点を持ちます。
勉強が中心になりすぎて心がすり減っていないか、子どもらしい毎日を送れているかを常に気にかけましょう。
特に小学校高学年で得られる経験は、のちの人生に大きく影響すると言われています。
適切なバランスで受験期間を過ごせると良いでしょう。
⑦第3者の意見にも耳を傾ける
夫婦で絶対受験させるべきだと考えが固執してしまうと、視野が狭くなってしまいます。
中には夫婦間でも受験をさせるべきかどうかで意見が分かれるケースもあるでしょう。
両親やどちらか一方の親のエゴとならない為には、冷静な目で判断できる他者の意見にしっかりと耳を傾けましょう。
たとえば、祖父母や友人、学校の先生や塾の講師など、中学受験に対する意見は様々なはずです。
最後に決めるのはご自身やお子さんなので、他者の考えを参考に自分たちの意見を固めると良いでしょう。
私たちの受検に対するスタンス
娘の受検を心配した理由
私たち夫婦が受検をさせることに対して、改めて心配した理由は以下になります。
考え出すと他にも色々と出てきそうです。
しかし、これらの心配事は「親のエゴではないか」という不安から生じたものでした。
私たちのエゴにならない為に
そう考えると、上述した親のエゴにならないポイント7選は、私たちにとってもヒントとなりそうです。
どれも意識するべきだと考えますが、中でも我が家は特にこの点を意識して受検にのぞむことにしました。
- 親が受検の主導権を握るが、子供の意見を十分に尊重する
- 受検のゴールを合格ではなく、娘の成長を一番の目的とする
- 自分の興味関心に対して、自発的に学ぶ力を身につけて欲しい
小学5年生が中学受験について必要な情報を十分理解することは難しいでしょう。
だからこそ正しい情報収集は親がするべきです。
私の場合であれば、都立中高一貫校受検に必要な情報を理解し、それを娘に分かるように伝えなくてはいけません。
そして、様々な意思決定についても、娘が最終判断を下すのは難しいはずです。
高校受験では子供の意見がより尊重されると思いますが、中学受験は親主導で良いと考えます。
ただ、十分に子どもの意思をくみ取るように努めないといけないでしょう。
言葉だけではなく、態度などから様々なサインを見落とさないようにすることも大切です。

親のエゴにならない為には、親子共に意見を出し合って理解を深めないとですね!
また、都立中高一貫校を目指す上で合格をゴールとしないという点も大切にしたいと思います。
「合格を目指さず受検対策するなんて甘い!」という意見もあるでしょう。
しかし、「合格」という結果だけを求めてしまうと、娘を心身ともに無理をさせてしまうのではいないかと、私たち夫婦は心配しています。
また、小学生の時にしかできない経験なども、しっかりと積んで欲しいと考えています。
だからこそ、結果よりも過程を大切にし、受検を通じて娘が大きく成長することを目標としたいと思います。
さらにいうと、学校や受検の勉強だけではなく、自分の興味関心について自主的に学ぶことができる子になって欲しいと願っています。
もちろん、積み重ねた努力の結果として合格というゴールにたどり着ければもちろん最高です。

受検を通して親子の絆をさらに深められればベストですね!
まとめ
今回は「中学受験は親のエゴなのか」という点について書いてみました。
親のエゴと言われるのは、様々な背景があります。
特に「親の価値観の押し付け」によって、子供が心身ともに疲弊するようなことは避けなくてはいけません。
まだ、小学生の段階で自分の進路を決めるのは難しいものです。
親が主導になるのは仕方がない部分ではありますが、お子さんの意思もしっかりと配慮したいものですね。
親のエゴにならないためのポイントも7つ説明しましたが、我が家は特に以下の点を意識することにしました。
そんな甘い考えなら最初から受験しない方がよいと言われるかもしれません。しかし、これが我が家にとって今出せる最適解かなと思っています。
なぜなら、子どもが成長するためのアプローチは一つでは無いですからね。そして、受験で結果が出ることが、子供や家族にとって唯一の幸せではないはずです。
この記事を読まれている方も、各家庭ごとで受験に対する方針が違って良いと思います。
ぜひ、ご夫婦やお子さんと意見交換をしながら、ご家族の中で最善の選択をしてみて下さいね!
さぁ次回はいよいよ受検意思が固まる第4回の家族ミーティングについてお話します。
それでは本日はこの辺で!