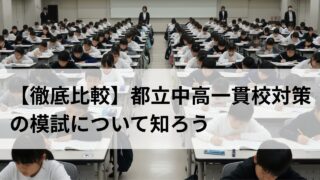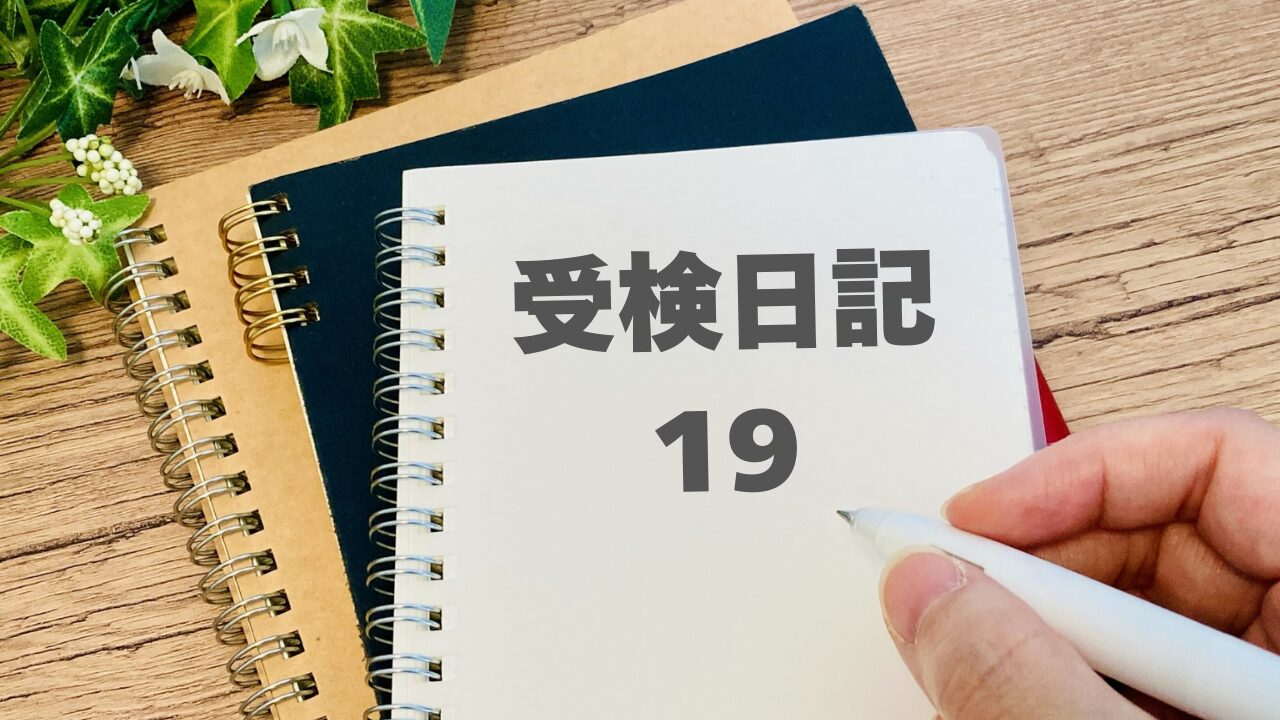こんにちは、よっさんです。
前回の受検日記#18では、家族で都立中高一貫校の文化祭に参加した際の感想についてまとめてみました。今回は、娘のこれまでの学習状況についてお話していきます。
娘は2025年の4月(5年生になるタイミング)からZ会の学習を開始しました。これまで受験日記をお読みいただいた方はご存じかと思いますが、目的は都立中高一貫校受検のためです。
気が付けば9月号が終わりましたので、半年が経過した形となります。現在、娘が受講しているのは、「小学生コース」の国、算、理、社4科目と目的別講座の「公立中高一貫校 適性検査(公適)」です。

今回は、Z会で受検対策を行った半年間を振り返り、学習状況や添削問題の結果、娘や私の感想などをまとめてみました。
結論から先に述べると
以上のような状況ですが、娘本人も私もZ会の学習に満足しています。ここから、上記の内容をもう少し詳しくまとめていきます。
「Z会の学習ってどんな感じなんだろう?」と気になる方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
期間限定で特典プレゼント
2026年2月27(金)〆切
受検日記#1から最新話までを一覧表にしています。「最初から読みたい方」「気になる話から読みたい方」は、こちらからどうぞ。
学習状況
受講科目
娘が受講している科目や講座はこちらです。
小学生コース ― 国語、算数、理科、社会
目的別講座 ― 公立中高一貫校 適性検査
Z会で小学生が受講できるコースは「小学生コース(紙教材)」「小学生タブレットコース」「中学受験コース」です。
中学受験コースは、国私立受験を目指すお子さんが対象となります。このコースは、都立中高一貫校を目指す娘にとっては適していないので、小学生コースまたは小学生タブレットコースから選ぶ必要がありました。
我が家は小学生コースを選んだのですが、一番の理由は紙教材である点です。また、5年生以上が受講できる目的別講座には、「公立中高一貫校 適性検査(5,6年生)」「公立中高一貫校 作文(6年生)」「作文(5,6年生)」とがあります。
作文が苦手な娘ですが、学習量が増えすぎる点を懸念して、5年生から受講できる作文講座は選択しませんでした。
受講講座の選択に関する考えや、公立中高一貫校の対策をZ会で行う場合はどの講座を選ぶべきかについては、過去記事にまとめています。興味のある方はこちらも参考にしてみてください。
学習時間は朝が中心
娘がZ会に取り組む学習時間のパターンは以下の通りです。
- 起床後から朝食までの時間
- 習い事が無い日の下校後
- 用事が無い土日祝日
- 弟の習い事中
この中でメインとなっているのが、①起床後から朝食までの時間です。だいたい時間にして20~30分くらいでしょうか。もともと他の学習を朝に行う習慣があったので、それをZ会に置き換えるだけでした。
また、我が家ではその時間帯に、娘だけではなく私や妻、小学2年生の息子も何かしら朝活をしています。

一家そろって朝活派なので、娘一人が頑張るという形ではないも良かったと思います!
また、上記のパターンの中で、娘が意外と集中できると感じているのが④弟の習い事中です。
小学2年生の息子の習い事に娘も付き添うのですが、見学できるエリアにテーブルがあるんです。約1時間半の間ですが、そこにZ会のテキストを持参して学習しています。なぜかこれが高い集中力をもってできているようです。

環境を変えて学習することも集中力高める効果ありですね!
テキストは全て終了(ほぼ月末までに)
Z会では、毎月テキスト(エブリスタディ)での学習と添削問題に取り組みます。テキストの学習は毎月欠かさず終了できています。
基本的には月末までに終わらせていましたが、体調不良や用事が多かった月などは数日遅れる月もありました。
小学生コースの各科目および公立中高一貫校 適性検査の1か月あたり学習量は以下の通りです。
- 国語・・・5回
- 算数・・・6回
- 理科・・・3回
- 社会・・・3回
- 公適・・・2 or 3回
各講座とも学習時間の目安は約40分となっていますが、実際はそれより短い時間で終わらせることの方が多いです。ただ、テキスト後半のハイレベル問題や公適に関しては、時間がかかることもありました。
添削問題の成績
添削問題も、テキストと同様にほぼ月末までに終わせることができていました。
成績に関しては、平均点以下になる月もありましたが、半年間でみると全ての科目で平均点以上となっています。
| 科目 | 娘の平均点 | Z会会員の平均点 |
|---|---|---|
| 国語 | 85.5 | 83.6 |
| 算数 | 88.2 | 84.7 |
| 理科 | 88.3 | 87.2 |
| 社会 | 90.8 | 85.8 |
| 公適 | 84.2 | 77.7 |
| 全教科 | 86.9 | 83.7 |
算数と社会、公適に関しては、Z会会員の平均点と比較すると良い点が取れていました。一方で国語、理科に関しては、ほぼ平均点に近い成績となっています。
Z会の学習を半年間続けて感じた事
娘が感じた事
- スマイルゼミで学習していた時よりも集中できている
- 学習カレンダーで「やる事が見える化」できる点が良い
- 一番苦手なのは算数で、特にハイレベル問題は難しい
- 一番好きなのは公適で、得意分野も自分で分かってきた
娘は以前スマイルゼミで数年間学習していました。最初は良かったのですが、徐々に学習が適当になってしまい、その失敗を繰り返さないためにもZ会は紙教材のコースを選んだのです。
Z会は紙の教材を選択したのは、スマイルゼミの反省点を活かすため(受検日記13)
結果的にこの選択は正解でした。娘にとっては紙教材の方が学習の集中力が高いようです。
教材がたまるデメリットはあるものの、整理の仕方を工夫しながらなんとかできています。

私はタブレットよりもZ会の紙教材の方が集中できているよ!
また、Z会の方が集中できた理由の一つが学習カレンダーです。
毎月自分で学習計画を立て、「科目名が書かれたシール」をカレンダーに貼ります。学習を実施したら「終わったシール」をその上に貼ります。
計画と実行した内容が「見える化」されることで、学習に取り組みやすかったようです。

計画は変更になることもあったけど、そんな時はすぐシールを貼り換えていたんだ。
学習の難易度に関しては、算数が一番難しいと言っていました。特にテキスト後半のハイレベル問題の難易度が高く、学習時間も毎回かかっていました。

学校で習わないことも出てくるから、なかなか理解できない問題も多いよ~。。。
一方で、思考力が問われる公適は得意だと感じているようです。実際に添削問題の成績も良い結果となっています。

特にグラフを読み取る問題と法則性を見つける問題が得意なんだ!
私が感じた事
- Z会の学習が習慣化&自走の土台ができて安心した
- 小学生コースの難易度は娘にちょうど良いレベル
- オンラインで添削問題を提出できる点が良い
- Z会以外の学習の必要性も少し感じる
まずはZ会の学習習慣がついたことは安心材料でした。また、受講開始前に「Z会は難しい」という口コミを見たことがありましたが、娘にとっては適切なレベルだったと感じます。そして、自分で計画を立てて取り組めており、自走できる土台がついてきた点も良かったです。

確かに難しい問題もありますが、頑張れば何とかなるレベルで挑戦しがいがあると思います。
また、紙教材を使っていますが、添削問題は郵送とオンライン提出が選択できます。オンラインの提出方法は、紙の答案用紙をアプリ上で画像を撮影し提出するだけです。
利便性を考えて最初からオンラインのみで提出していますが、何と言っても返却までが早いです。すぐに結果が知ることができ、アプリ上で赤ペン指導の内容も確認できます。
さらに良いと感じた事は、添削済みの画像データがZ会側で印刷され、紙の答案用紙が返却される点です。

返ってきた答案用紙はファイリングしておくと、すぐに復習できるのでオススメです!
Z会の学習内容に満足しているものの、一方で「これだけで受検対策として足りるのか?」という懸念もあります。
Z会の公適では、思考力を問う質の高い問題が出題されますが、一方で演習量は多くありません。様々な問題に慣れるためにも、市販の教材等で補う必要があるかもしれません。
また、適性検査では記述力が非常に重要です。娘は作文が苦手ですが、本格的な対策はまだできていません。これに対しては、早急に何か記述力アップの取り組むべきだと感じました。

半年間でZ会の学習ペースがつかめたので、10月から新たに作文対策を始めることにしました。
まとめ
今回はZ会の学習が半年間を経過したので、学習の振り返りをまとめてみました。
- 毎月ほぼ予定通り学習が進められた
- 添削問題の成績は、全ての科目が平均点以上
- 親子共にZ会の教材に満足している
- リズムはつかめたので、少しずつ学習の負荷を増やす予定
Z会の学習が半年間が過ぎたというのは、都立中高一貫校の受検対策も半年間が経過したということです。
気が付けば、試験本番(2027年2月3日)まで500日を切りました。親子共に手探りで始めた挑戦ですし、今取り組んでいるかことが合格に繋がるかどうかは未知数です。
しかし、娘が今取り組んでいることは、受検の合否に関わらず将来必ず役立つことだと確信しています。
結果も重要ですが、過程と家庭を大切にする都立中高一貫校受検にしたいと改めて思います。
都立や公立中高一貫校を目指す皆さんにとっても、最高のチャレンジになることを願っています。今後も共にお子さんを支えていきましょうね。
それでは本日はこの辺で!